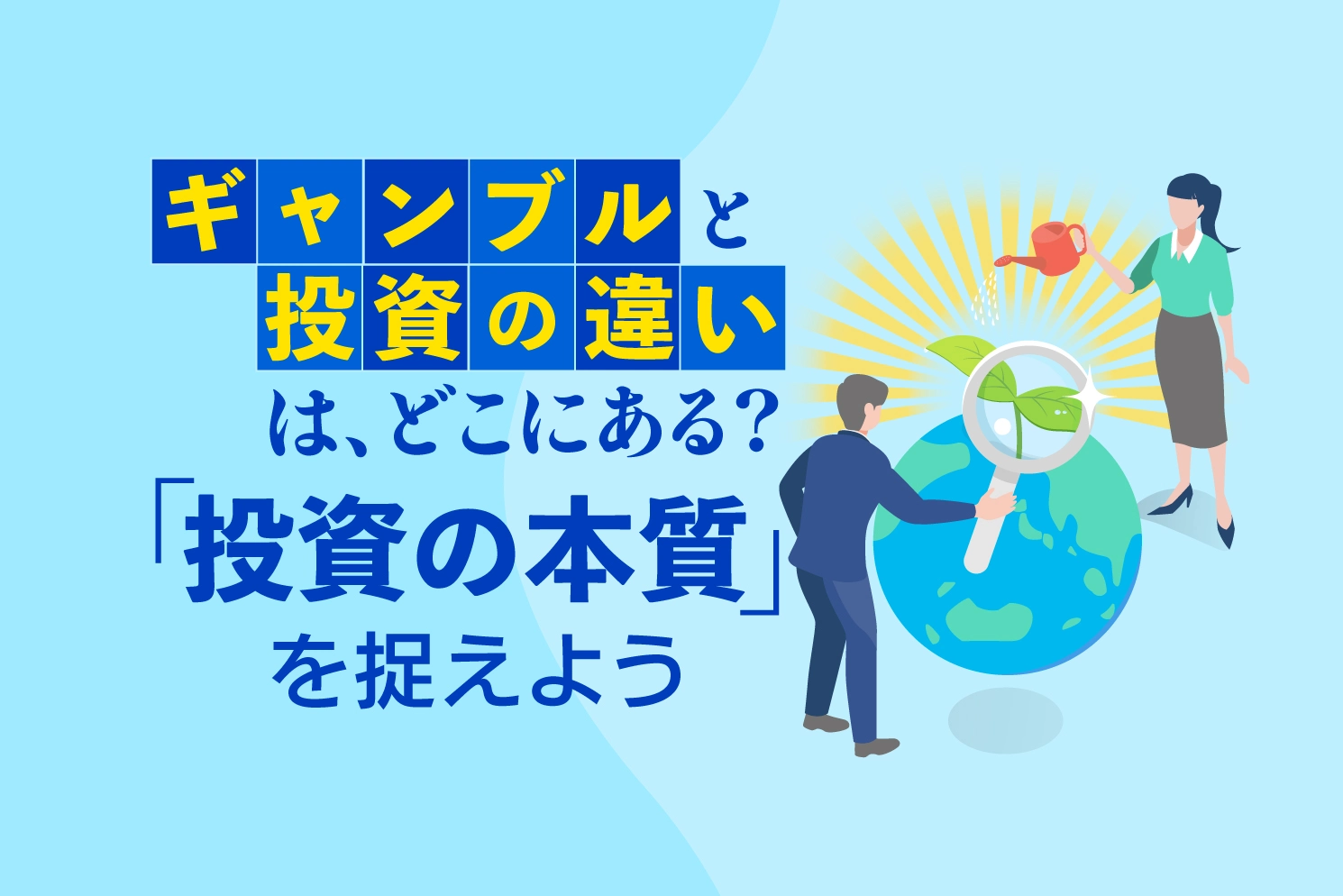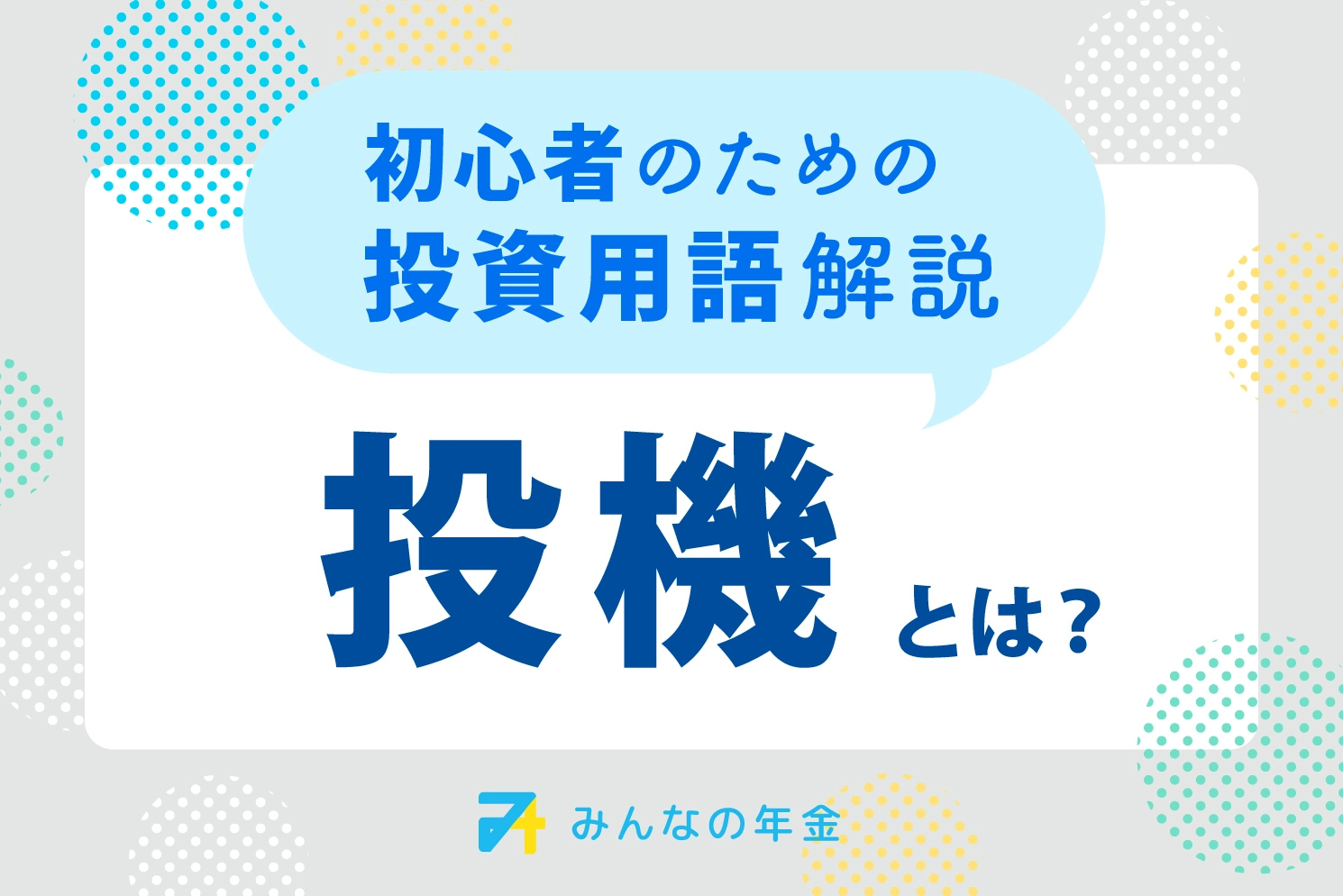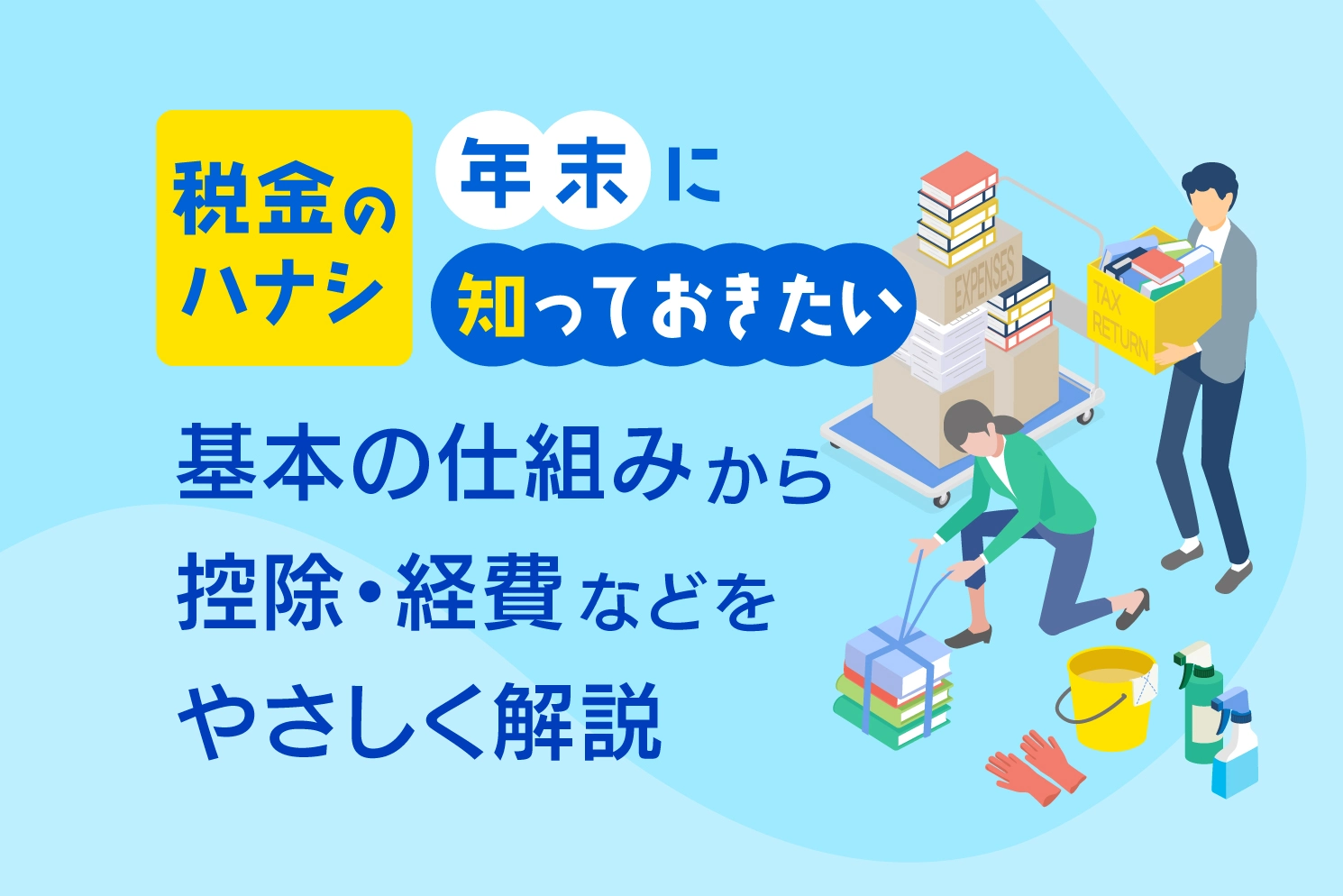リスクに違い!? ファンドの「利益の出し方」から考える投資判断【不動産クラウドファンディング】
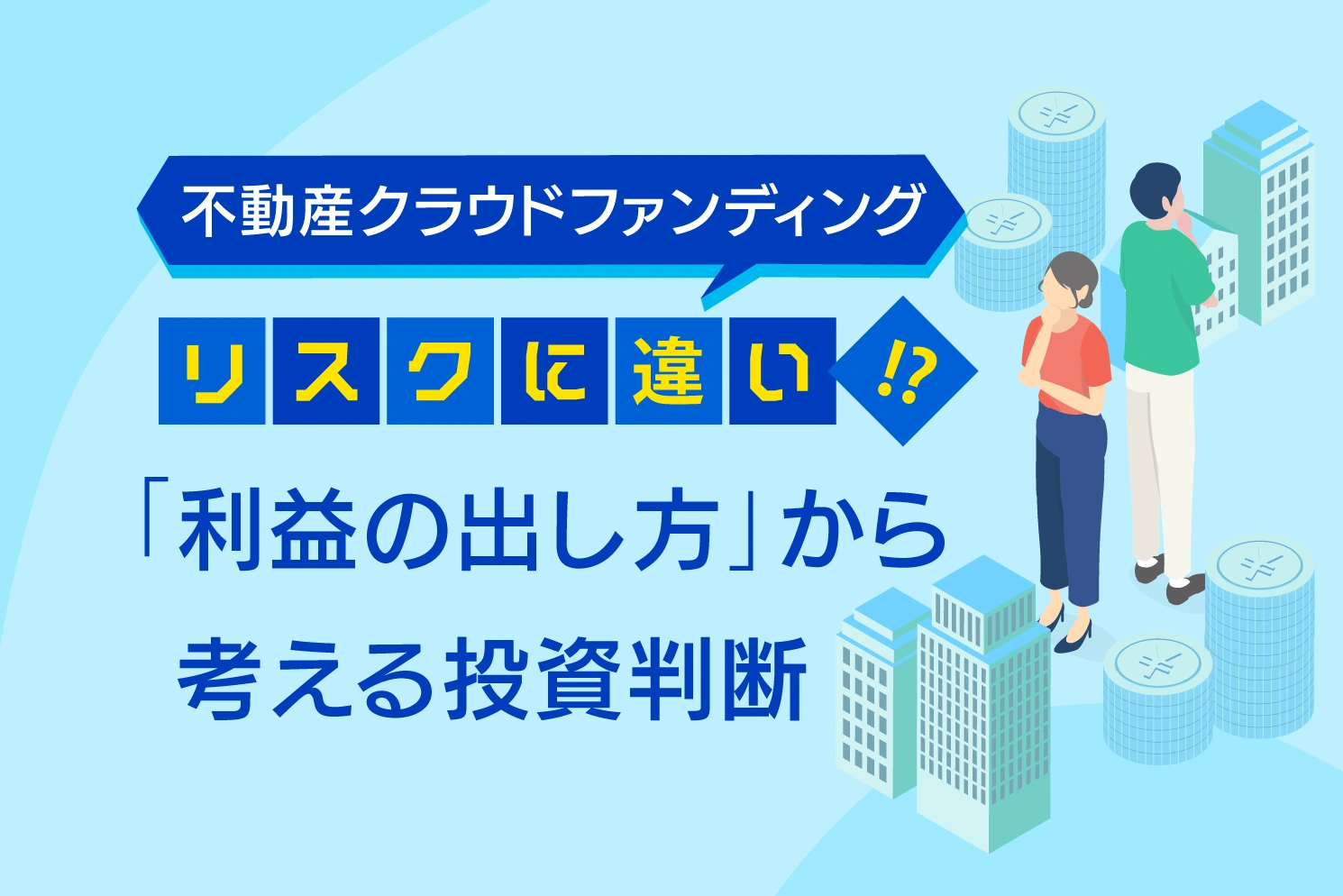
不動産クラウドファンディング業界で起きていること
不動産証券化・小口化の市場は、2016年から右肩上がりで拡大しており、2024年12月時点で40.8兆円にまで成長しています。
不動産証券化として、近年新しくマーケットとして認知されてきたのが「不動産クラウドファンディング」です。
現物不動産の購入よりも手軽で、インターネットから申し込みできることもあり、多くの方が資産形成の第一歩として利用しています。
その一方で、ニュースなどでは「分配金が遅れている」「償還が延期された」といった事例を目にし、不安を感じた方もいらっしゃると思います。
実は、こうした事例は不動産クラウドファンディング全体の問題ではなく、ファンドの「利益の出し方」によって起こりやすいリスクの違いがあります。
今回は、不動産クラウドファンディングのファンドのタイプ、「開発型」と「完成済み物件型」について、それぞれの利益の出し方の違いを中心に解説します。
参考:不動産私募ファンドに関する実態調査(2025年1月)一般社団法人不動産証券化協会
開発型ファンドとは

「開発型ファンド」とは、土地や未完成の建物を仕入れて、開発や再販で利益を出すことを前提に組成されるタイプです。
不動産クラウドファンディングの事業者が、独自のノウハウで土地代などのコストを下げ、さらに市場価値を大幅に高めることができる企画(デザイン性の高い住宅、利便性の高い商業施設など)を盛り込むことで、売却益の最大化を目指します。
魅力は高い想定利回り
売却までの不確実さがそのままリスクに
- 更地の取得から建設、売却まで予定通り実行されることが前提となるため、認可の遅れや施工業者とのトラブル、資材価格の高騰などにより、工期が延び、予定された収益が減少する可能性が。
- 開発後の物件を売却する際に、市場環境の変化によって売却価格が想定よりも低くなることも。
つまり、開発型は大きなリターンの可能性がある一方で、出口(売却)の不確実さが直接リスクになるのです。
「想定通りにいけば魅力的だが、計画が崩れると投資家への分配が不透明に」
――これが開発型の特徴です。
最近増えているのが、割安に取得した物件をリノベーションなどで市場価値を上げ、家賃収入(インカムゲイン)と売却益(キャピタルゲイン)の両方を最大化する運用スタイルです。
不動産投資の世界ではバリューアッド型と呼ばれますが、今回の「利益の出し方」に焦点を置いたご紹介の中では、開発型に含めています。
このバリューアッド型は、従来の開発型よりもリスクが抑えられているため、近年ファンド数が増加傾向にあります。
開発型は、これから建てるものに対して出資するものです。
どこに何を建てて収益を上げるのか。開発計画は現実的か。そういう視点も投資判断に必要となるでしょう。
完成済み物件型ファンドとは

一方で「完成済み物件型」は、すでに完成して稼働している不動産を対象にするファンドです。
正確性が高く、安定した運用が期待できる
- 既にある物件のため、開発や許認可といった配当遅延につながるような不確定要素が少なく、収益計画が立てやすい。
- 建物はすでに完成しているため、すぐに賃貸運用を開始できる。
安定しているからこそ、利回りは上がりにくい
- 安定しているからこそ、開発型のような想定利回りを大きく上回ったリターンとなりにくい。
- 物件の買い手の都合によって、想定していた価格で売却できなかったり、売却が遅れたりするケースも。
- 借主の滞納などにより、分配金の原資となる賃料収入が減少するリスクがある。
中長期での運用の場合、空室率の上昇や賃料相場の下落が起こることも。特に、オフィスや商業施設は景気の影響を受けやすい。
完成済み物件型は、安定的な運用が可能だからこそ、飛び抜けた利回りにつながりにくいのは事実。
だからこそ、「利益は出てほしいけど、それ以上に損する方が嫌」という方や、大きなリターンよりも「安定感」を重視したい方は完成済物件型ファンドの方が向いているでしょう。
コツコツとお金を貯めるのが得意な方にもおすすめです。
一方、中長期運用のファンドの場合は、期間が長くなる分のリスクが織り込まれているので、想定利回りがやや低くなりがちです。
とはいえ、短期間で次々に運用を回すのが面倒な方や、ほったらかし投資としてのリスク分散先としては手堅いと言えます。
『みんなの年金』は安心できる?
当社が運営する『みんなの年金』は、完成済み物件型に特化しています。
この仕組みにより、売却トラブルによる分配遅延のリスクを抑え、完成済み物件型の中でも、投資家の皆さまに安心して資産形成に取り組んでいただける環境を整えています。
運用期間も最長で約1年という短めのファンドばかりなので、中長期運用のデメリットの影響を受けにくい運用でお客様へ利益を分配します。
そのような仕組みにより、『みんなの年金』は、完成済み物件型の中では高い想定年利回りである、8%をキープし続けています。
※『みんなの年金』のファンドはハイブリット型やインカム型キャピタル型などがあります。くわしくは、各ファンドの詳細をご確認ください。
▼2パターンの売り先について、くわしくはこちら
自分のリスク許容度でファンドを選ぶ
「多少リスクがあっても、大きなリターンを狙いたい」
→ 開発型の方が満足度が高いかもしれません。
「安定した分配や見通しを重視したい」
→ 完成済み物件型の方が納得感があるでしょう。
どちらが正解というわけではありませんが、自分のリスク許容度に合ったファンドを選ぶことが大切です。
不動産クラウドファンディングに限らず、高い利率が期待できる投資商品は、リスクも大きくなりがちです。そこを常に意識して、ファンドを選ぶようにしましょう。
ファンドだけじゃなく、運営元もチェックしよう
不動産クラウドファンディングは、不動産への直接投資ではなく企業の不動産事業への出資です。
不動産クラウドファンディングは、不特法により国からの認可がなければ運営できない事業ではありますが、投資である以上、ファンドの内容と合わせて、運営会社の事業計画の詳細、過去の実績なども調べることをおすすめします。
また、もう一つ注目したいポイントは、各事業者のサービス理念や戦略的特徴です。
『みんなの年金』は、公的年金問題を解決したいという思いから生まれたサービスで、公的年金とは違った、お客様の新しい‟当たり前”になることを目指しています。
そのため、公的年金と同じように2カ月に一回、分配があります。
また、『みんなの年金』のファンドが都市部のマンション物件ばかりなのは、運営会社である株式会社ネクサスエージェントが得意とする分野だという点も特徴と言えます。
世の中には、公益性の高さ、地域密着、土地だけに特化など、さまざまな理念や事業者の強みを生かしたサービスが存在します。
ファンドを選ぶ際に、サービス理念や方針への共感を投資判断の材料にしても良いでしょう。
▼『みんなの年金』の強みや、不動産クラウドファンディングについて詳しくはこちら
しっかりと納得できる投資を
最近の不動産クラウドファンディングで報じられているトラブルは、多くが「開発型」で発生しているものです。
一方で『みんなの年金』は完成済み物件を対象にし、購入前に2パターンの売却ルートを確認してからファンド化することで、配当遅延などが起りにくくなるように対策しています。
投資はリスクを完全になくすことはできませんが、仕組みを理解し、構造を知ることで、納得感を持って臨むことができます。
もちろん、投資の基本である「資産を分散させる」ことも重要です。
『みんなの年金』は、皆さまが安心して資産運用に取り組めるよう、これからも透明性と安定性を大切に運営してまいります。
▼『みんなの年金』のファンドや運用実績について、さらに詳しく知りたい方はこちら▼
※本記事の情報は、当社が信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性が保証されるものではありません。本記事は公開日時点の法律を基準に執筆しています。また、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、個別の状況に応じた内容ではありません。個別の話題については、必ず各分野の専門家にご相談ください。

初心者でも始めやすい
不動産投資といえば『みんなの年金』
買取・販売・賃貸管理を通して、不動産を活用した資産運用コンサルティングや不動産データプラットフォームの運営を行う、ネクサスエージェントが提供するサービス『みんなの年金』。
多岐にわたる事業で培ったノウハウを活用し、これまで「元本割れゼロ、配当遅延もゼロ、年利回り実績8%」という業界高水準でのファンド運用を実現しています。