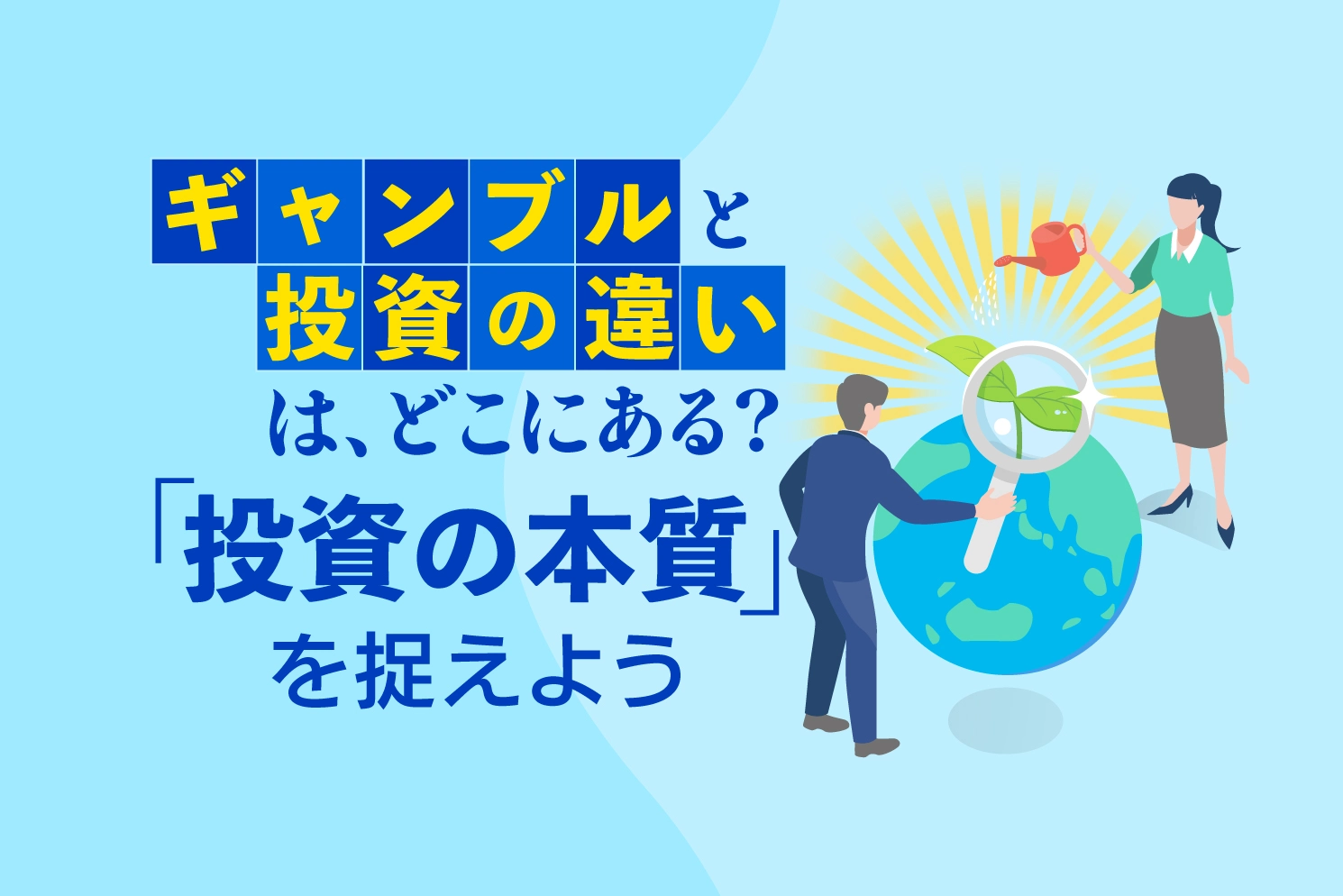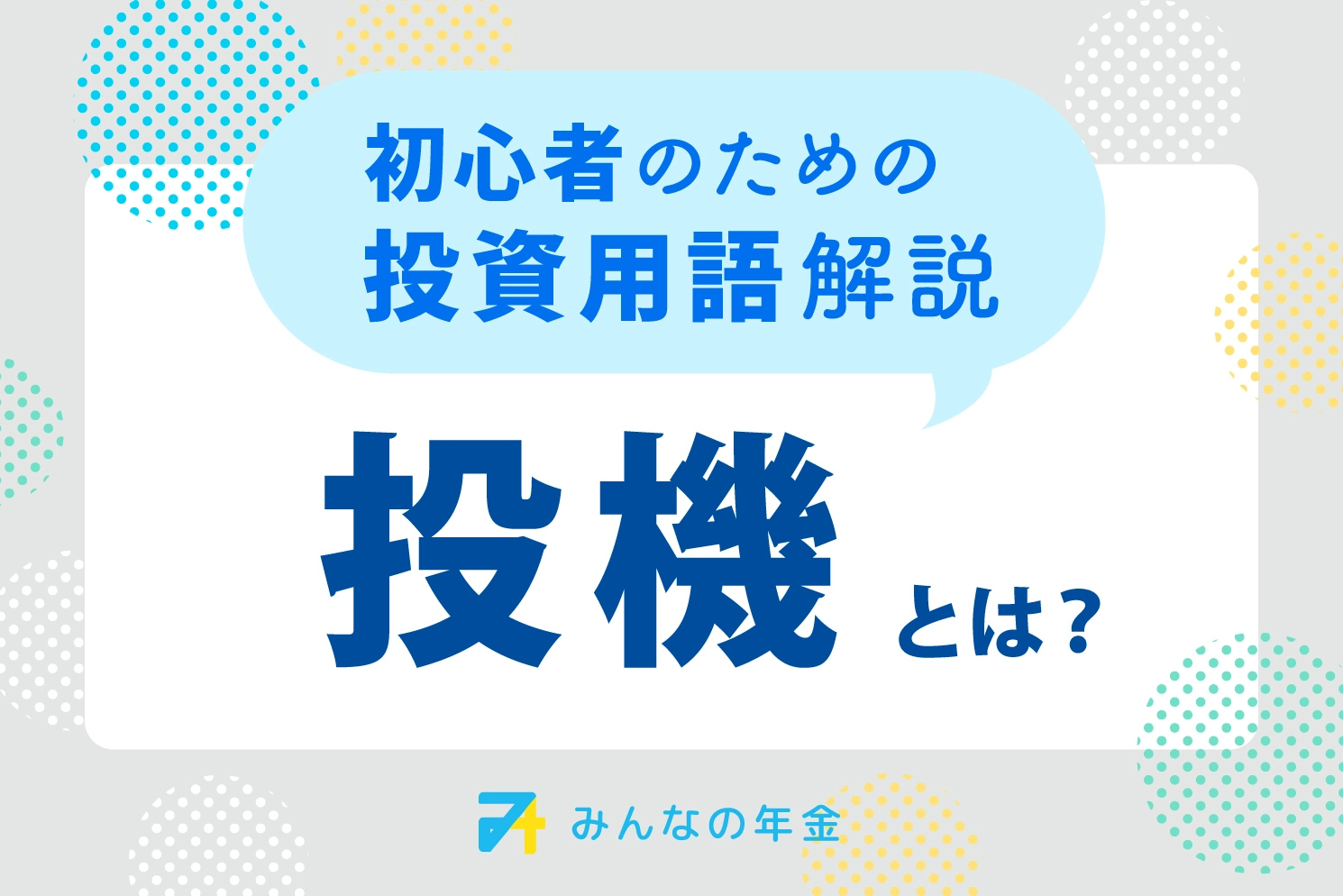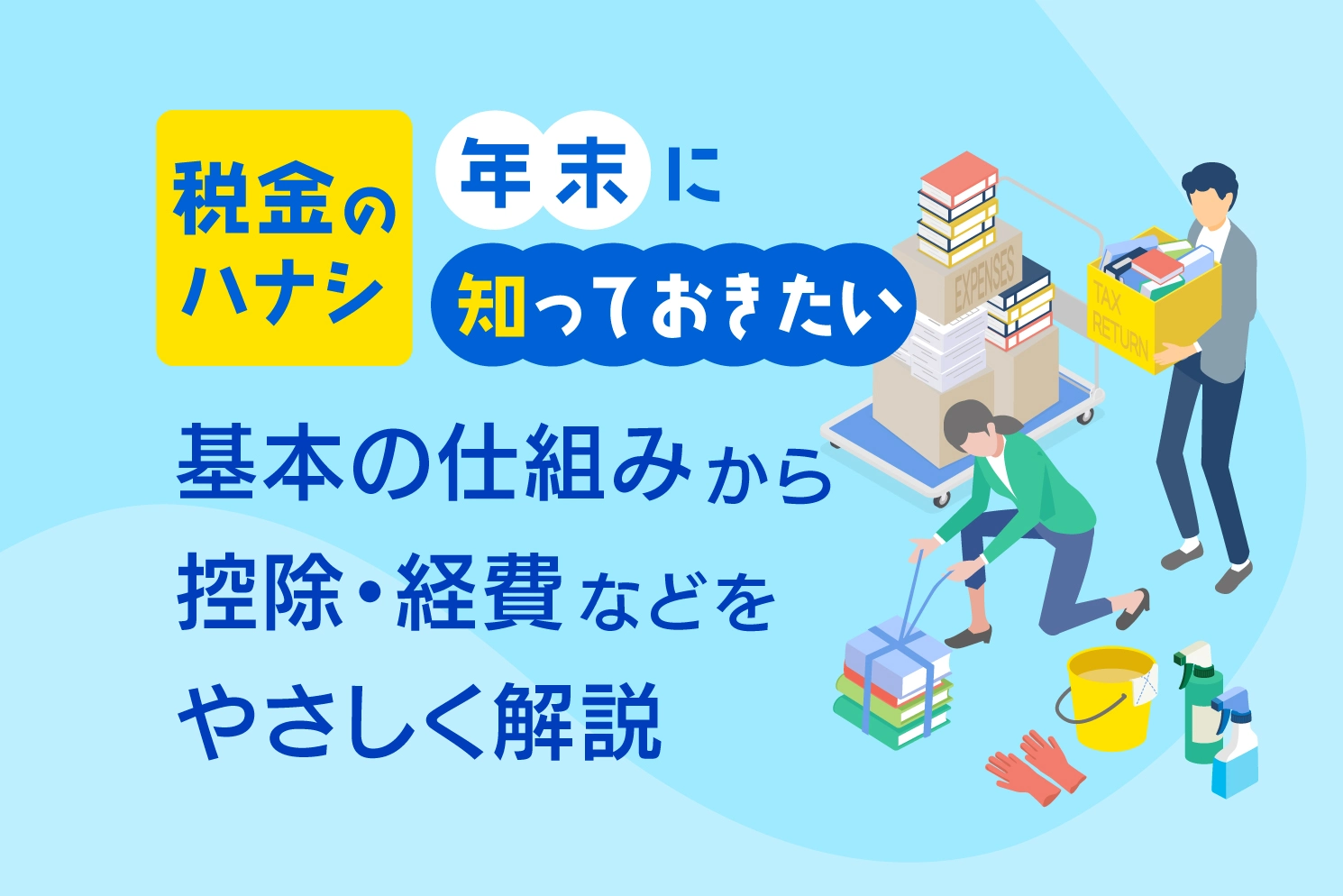ふるさと納税・ポイント還元制度の締め切り迫る【2025年】

不動産投資で税負担を圧縮するのと同様に、ふるさと納税もまた、賢い資産形成に欠かせない「税金最適化」の一種とも言えます。
ふるさと納税ではこれまで、一部の寄付ポータルサイトを通じて、寄付額に応じたポイント還元を受けられる仕組みがありました。
返礼品だけでなくポイント還元もあることで、「節約しながら応援できる制度」として、制度を最大限活用していた方も多いのではないでしょうか。
しかし、2025年10月1日から、すべてのふるさと納税ポータルサイトにおけるポイント還元が禁止されることが決まっています。
もし、今年のふるさと納税がまだであれば、大きなリターンを受け取れる最後のチャンスかもしれません。
2025年9月末までがラストチャンス。
今だからこそ、制度を味方につける選択をしよう
今までの制度を使って最大限に‟お得”を享受するには、まさに「今」ふるさと納税するのがおすすめです。
なぜポイント還元が廃止に?
ふるさと納税は、返礼品やポイントをもらいながら、自分の故郷や応援したい地域に寄付できる制度ですが、なぜポイント還元だけが廃止されるのでしょうか。
利用者間の不公平をなくすため
ポイント還元は特定のサイト経由の寄付が対象だったため、同じ金額を寄付しても、サイトによって「経済的利益」に差が出てしまうという不公平な状況に。
また、ふるさと納税が本来の趣旨から外れ、ポイ活(ポイント活動) の一環として利用される現状も総務省から問題視されました。
制度本来の目的である「地方創生」が形骸化
ふるさと納税サイトの過度なポイント還元競争により、資金力のある自治体が有利になるという不公平な状況が生まれていました。
これにより、制度本来の目的である「地方創生」が形骸化してしまう事態に。
以上の理由からポイント還元が廃止され、10月以降は制度の本質に立ち返ることになります。
今年のポイント還元は、「最後のボーナス期間」として活用しておくのが良いでしょう。
ちなみに、全面的に禁止されるのは、ふるさと納税の仲介サイトによるポイント付与のみです。
寄付時に使用するクレジットカード会社が提供する、通常のポイントやマイルは、引き続き付与されます。
ポイントがなくなっても、ふるさと納税は“損”じゃない
ふるさと納税の最大のメリットは、「実質的に自己負担を抑えながら、税金の使い道に意志を反映できる」点です。
- 応援したい自治体や地域産業に、意思を持って納税できる
- 控除限度内であれば、住民税・所得税の一部が減額される
さらに、納税者にとって必要な日用品や備蓄品などを返礼品として選ぶことで、実質的な生活費の軽減につながります。
しかも、単に返礼品を受け取るだけでなく、応援したい自治体や地域産業に自分の納税を通して直接貢献できるという大きな意義があります。
注意点としては、これは節税ではないということです。
支払う税金の総額そのものが減るわけではなく、あくまでも「どこに納めるか」「その税金がどう使われるか」を自分で選択できる制度であると考えましょう。
税制メリットを活かした老後の準備制度・iDeCoという選択肢
ふるさと納税が「今の生活を支える制度」だとしたら、将来に向けて備える制度としてよく挙げられるのが、iDeCo(個人型確定拠出年金)です。
iDeCoは、自分でお金を積み立てて運用し、60歳以降に受け取る「じぶん年金」のような仕組みです。
「長期でコツコツ老後資金を準備したい」「所得が高くて税負担が重い」「資産運用に前向き」などの条件に当てはまる人にとっては、有力な選択肢のひとつとなる制度です。
iDeCoの主なしくみ
- 掛金が全額「所得控除」の対象に
- 運用益が非課税
- 受け取り時にも控除(退職所得控除、公的年金等控除)が使える
たとえば、会社員が月23,000円(年間276,000円)を拠出すると、その分課税対象所得が減るため、所得税・住民税が軽くなる仕組みです。
iDeCoの注意点
iDeCoには一定のメリットがある一方で、いくつかの注意点や制約もあります。
- 原則60歳まで引き出せない(途中で使えないお金になる)
- 運用によっては元本割れのリスクもある
- 掛金の上限は職業ごとに異なるため、税金の圧縮効果も人それぞれ
▼こちらの記事でもiDeCoを解説しています
ふるさと納税とiDeCoの共通点、それは税金の控除
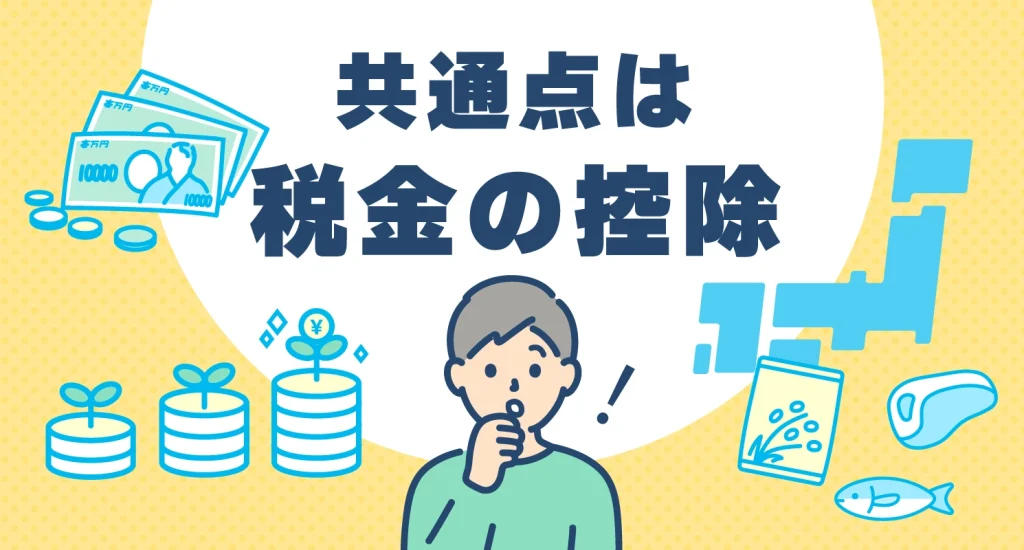
どちらも「税金の軽減」に直結する制度ですが、仕組みは少し異なります
| ふるさと納税 |
| iDeCo |
|
|---|
ふるさと納税の控除は、単に「税金が安くなる」というよりは、本来住んでいる自治体に納める税金の一部を、応援したい自治体に「寄付」という形で前払いし、その分を税額から差し引くという仕組みになっています。
iDeCoは、掛金が全額所得控除の対象となります。
つまり、支払った掛金が課税所得から直接差し引かれる=所得税と住民税の両方が軽減されるということです。
iDeCoの利用がふるさと納税の控除上限額に影響する
iDeCoを利用して掛金を拠出すると、その分だけ課税所得が減り、それに伴ってふるさと納税の控除上限額も下がってしまうのです。
ということは、「iDeCoを始めたら、ふるさと納税の控除上限額が下がって損をするのではないか?」という疑問が出てくるかと思います。
実際のところ、どちらを優先すべきでしょうか?
一般的には、iDeCoとふるさと納税は併用がおすすめです
iDeCoの所得控除によって課税所得が減ると、ふるさと納税の控除上限額は確かに下がります。
しかし、その影響はiDeCoで得られる税負担の軽減額と比べて小さいことがほとんどです。
iDeCoとふるさと納税を併用すると、iDeCoによる大きな税金軽減の恩恵を受けつつ、ふるさと納税でも実質2,000円で返礼品を受け取れるため、単独で利用するよりもトータルで大きなメリットが得られることが多いでしょう。
ふるさと納税とiDeCo、それぞれの特徴を理解して
どちらも“税金との付き合い方を考える”きっかけになる制度です。
仕組みと影響を理解することで、それぞれのメリットを最大限に活かし、賢く税負担の圧縮や資産形成を進めることができます。
【NISAは関係ないの?】
NISAは「非課税制度」であり、投資で得た利益(売却益や配当金)にかかる税金(通常20.315%)をゼロにする仕組みです。
NISAの利用そのものが、所得控除のように課税所得を直接減らすことはありません。
参考:総務省|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の概要
参考:iDeCoの概要 |厚生労働省
さらにその先へ。資産を「育てる」選択肢も
資産形成には様々な手段がありますが、リスク分散として不動産投資という手段も。
不動産クラウドファンディング
このコラムの運営をしている『みんなの年金』は、不動産クラウドファンディングのサービスです。
投資初心者の方や、分散投資先としてもおすすめです。
- 少額から始められる
- 忙しい人でも手間がかからず‟ほったらかし”で運用可能
- ファンド形式だから、投資初心者もはじめやすい
- 分配金が「じぶん年金」のような役割に
不動産クラウドファンディングにご興味を持たれましたら、『みんなの年金』を是非ご検討ください。
↓予定年利回り8%、これまで元本割れゼロ、配当遅延もゼロで運用中!↓
▼不動産クラウドファンディングについて知りたい方はこちら
現物不動産投資
- 家賃収入で毎月安定収入を得られる
- 減価償却などで所得圧縮による税負担の軽減も可能
- 長期保有による資産形成や、相続対策にもつながる
まずは不動産クラウドファンディングで“触れて”、興味が深まったら実物投資へ──。
段階的にステップアップできるのが、今の不動産投資の魅力です。
『みんなの年金』運営会社であるネクサスエージェントは、不動産による資産運用のご相談を受け付けています。
もし相談してみたいという方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
▼現物不動産投資について詳しくはこちら
制度を“使う人”が、未来をつくっていく
ふるさと納税やiDeCoなどの制度は、使い方次第で生活や未来を支えてくれる仕組みです。
不動産投資は制度ではないものの、資産形成の選択肢として現実的かつ強力な手段のひとつ。
制度を活かすも、資産を育てるのも、選ぶのは自分自身。
未来は、“選択”で変わります。
豊かな未来のために、自分に合った資産運用方法を選んで活用していきましょう。
※本記事の情報は、当社が信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性が保証されるものではありません。本記事は公開日時点の法律を基準に執筆しています。また、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、個別の状況に応じた内容ではありません。個別の話題については、必ず各分野の専門家にご相談ください。

初心者でも始めやすい
不動産投資といえば『みんなの年金』
買取・販売・賃貸管理を通して、不動産を活用した資産運用コンサルティングや不動産データプラットフォームの運営を行う、ネクサスエージェントが提供するサービス『みんなの年金』。
多岐にわたる事業で培ったノウハウを活用し、これまで「元本割れゼロ、配当遅延もゼロ、年利回り実績8%」という業界高水準でのファンド運用を実現しています。